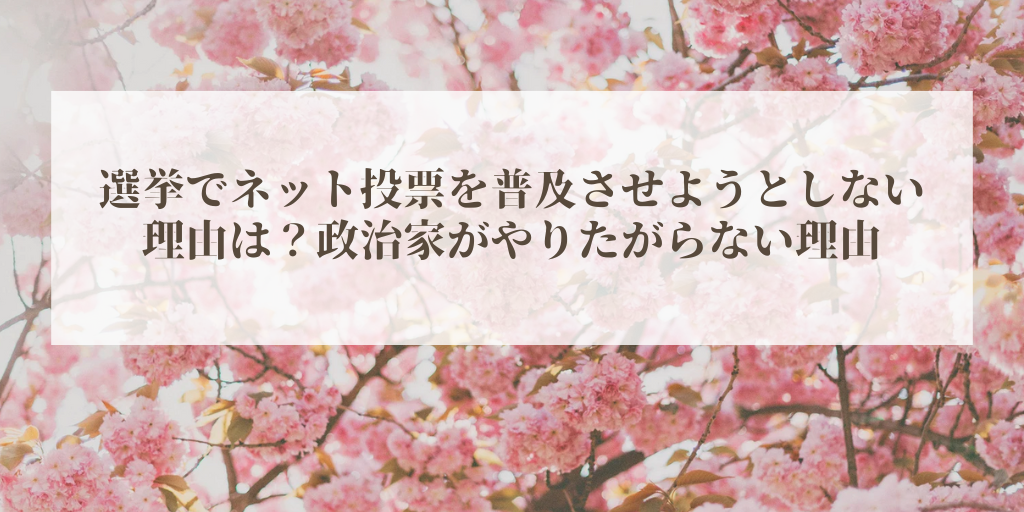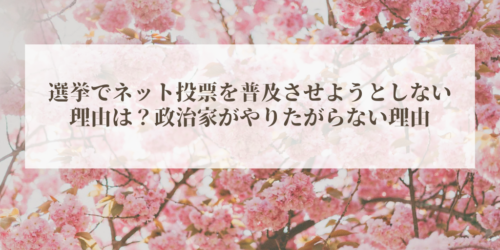10月27日は総選挙(衆議院議員選挙)です。
今回は石破政権が発足してすぐの解散総選挙で、石破政権の信任選挙とも言われていますが投票率はどうなるのでしょうか?
自民党総裁選は事実上の首相を選ぶ選挙で派手に報道されましたが、投票権は議員と自民党員に限られます。
野党は自公を過半数割れに追い込もうとしていますが、そのためには浮動票と言われる無党派層をどうどう取り込めるかだと思います。
投票率を上げるには、ネット投票も一つの手段だと思います。(これが全てだとは思いません)
なぜネット投票が普及しないのか?政治家が本当はやりたがっていないのではないかと考え、検証してみます。
ネット投票とは
ネット投票(オンライン投票)とは、投票所に行かずにオンラインで投票できる制度のことを言います。
ネット投票が実現すれば、自宅にいながらパソコンやスマートフォンから投票ができ、障害のある方や怪我をしている方などの移動や付き添いについて考慮しなくてもよくなるため、負担が減るでしょう。
ネット投票には他にも以下のようなメリットが期待できます。
- 開票作業が速い
- 選挙管理の人的・金銭的コストを減らせる
電子投票との違い
ネット投票と混同されやすいものに「電子投票」があります。
電子投票とは、投票所に設置された端末を用いて投票することです。ネット投票とは違い、投票所に行かなくてはなりません。
ネット投票実現への課題
課題の1つとして、法改正が必要ということがあります。
公職選挙法では「自ら投票所に行き、投票をしなければならない」と定められており、遠隔での投票は認められていないため、ネット投票は認められていません。
第四十四条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
引用元:公職選挙法
でも、これって法改正すればいいだけですよね。
実現するには、以下のような課題があるといわれています。
他にも、以下の3つの課題があります。
- 本人確認
- 投票の秘密の確保
- 安定したシステムの確保
でも、せっかく導入した「マイナンバー」を使った方法が考えられないのでしょうか?
ネット投票は、北欧のエストニアなどで導入済みだそうです。
つくば市の取り組み
選挙の投票は法律で、決められた投票所に本人が出向くことが原則とされている。
この仕組みを大きく変えようとしているのが茨城県つくば市です。
国家戦略特区「スーパーシティ」としてさまざまな実証実験が国から許可された、いわば実験都市でもある。
特区の枠組みを活用し、2024年10月の市長選挙と市議会議員選挙で、全国初のネット投票の実用化を目指しています。
政治家が考えそうな反対する理由を考えると
一番票を入れてくれる高齢者層がネット出来ないから?
若者の投票行動を制限したいという政権与党の意思の表れ?
ある与党前職の関係者はこう警戒しているそうです。
「若年層がネットで投票するとユーチューバーやインフルエンサーに票が流れるのでは」
でも、与党ですら政治とは程遠い有名人などを候補に起用しているから、そもそも候補者選定の問題なのでは?
先日の都知事選での候補者乱立で候補者掲示板が足りなくなった件などは、デジタルサイネージなどのデジタル化を勧めればポスターの人海戦術などの不公平だって無くなるはず。
地方選挙制度をある程度自由にさせて実績を積み上げるくらいしないと、おこるがどうかもわからない不正を盾にして、永遠にネット投票なんかできないのではないかと思うのです。